絵本作りに興味はあっても、このような悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
ネットで調べてみても、ざっくりとしか書かれていなくて理解できずに作るのを諦めてしまう、なんて方もいらっしゃるかと思います。
実は物語の作り方はとっても簡単で、『5つのステップ』を意識すれば、誰でも作ることができるんです!
「作れない…」と諦めてしまう前に、こちらの記事を読んで、オリジナルの『絵本』を作る際のコツを理解してみてはいかがでしょうか?
1、物語の作り方 〜5つのステップ〜
物語をつくろうとしてみたけど、どうやって物語を考えていけばいいのか、悩む人も多いのではないでしょうか。
この章では、物語の作り方を5つのステップで詳しく解説していきます。
- ①ターゲットを決める
- ②テーマを決める
- ③登場するキャラクターを考える
- ④構成を考える
- ⑤実際に書く
上記が物語を作る際に必要となるステップです。
しっかりとポイントを抑えることで読まれやすい絵本を作ることができます!
ポイントを抑えて素敵な絵本を作っていきましょう♪
①ターゲットを決める
はじめに誰に読んでもらいたいのか、どんな人に読んで欲しいかを考えましょう。
例えば「保育園にいる子どもにみてもらいたい」と思ったとします。
しかし保育園には0〜6歳まで、幅広い年齢の子どもたちがいます。
5歳の子どもが0歳向けの絵本をみても、お話が簡単すぎてすぐに飽きてしまいます。
反対に0歳の子どもが5歳向けの絵本を見ても、さっぱりわかりませんよね。
ここでいう『ターゲット』は『年齢をしっかり絞る』ということです。
保育園・幼稚園ではhクラスが乳児・幼児で分かれています。
- 0・1・2歳児 赤ちゃんクラス・乳児 音・色・形を読む絵本
- 3・4歳児 年少クラス 簡単な物語であれば見ることができる
- 4・5歳児 年中クラス ある程度の絵本は飽きずに見ることができる
- 5・6歳児 年長クラス 長めの絵本でもしっかりと見ることができる
(年齢別のおすすめ絵本は一番下に記載してます。)
それぞれの年齢で楽しく見れる絵本が変わってきます。
赤ちゃん向けに絵本を作るのか、それともストーリーをしっかり練った年長児向きの絵本を作るのか…はたまた保育園児以上の年齢向きなのか、しっかりと対象の年齢を考えましょう!
ターゲットが決まらない、という方は月齢別で他の絵本を見てみたり、テーマやキャラクターを先に考えてみましょう!
②テーマを決める
一見、難しそうに感じるテーマ決め。
「アイディアが全く出てこない…」と悩まれる方も多いかと思いますが難しく考える必要はありません!
絵本は主に子ども向けの本です。
子どもたちは身近にあるもののお話の方が頭に入ってきやすいのです。
食べ物、乗り物、友達、おもちゃ、文房具、家電…などなど
その他にも楽しい・嬉しい・暑い・寒い・思いやりなどなど…子どもたちの疑問や感情をテーマにしてみても面白そうですね!
絵本には無限の可能性があります。身近なものからテーマとして使えそうなものがないか、探してみましょう!
③登場するキャラクターを決める
お次はキャラクター決めです。
テーマを『家電』としたならば、登場人物は洗濯機や冷蔵庫たちになりそうですね。
もちろん、『家電を使うお母さん』『家電を使う僕』をキャラクターにしても問題ありません。
”家電を使う日常”を描いた絵本なのか、”家電たちが楽しく暮らす世界”を描いた絵本なのか…テーマを掘り下げていくと、自分が描きたいストーリーが見えてくるはずです。
テーマを元に、どのような世界を描きたいかを考えてみましょう。
④構成を考える
①〜③まで考えたら、次は構成を考えましょう。
構成のなかで大切なポイント・子どもたちに喜ばれるポイントがあります。
- 起承転結を意識して書くこと
- 繰り返しを入れること
この二つがキーになります。
起承転結を意識して書く
まず”起承転結を意識して書く”について説明します。
- 「起」…物語の始まり。背景などを説明する。
- 「章」…本題に繋がる導入部分・トラブルや事件の発生
- 「転」…始まりから続いていたストーリーにアクセントをつける。物語で一番伝えたい内容。
- 「結」…「転」の後に何が起こったのか。物語の締めくくり。
“起承転結”は物語を作る上でとても大切なポイントになります。
繰り返しを入れる
⚪︎次に”繰り返しを入れる”について説明します。
絵本には同じパターンを繰り返していたり、同じ言葉が繰り返し使われている表現が多くあります。
昔からある有名な絵本をみてみましょう。
「大きなかぶ」「3匹のこぶた」「オオカミと7ひきのこやぎ」どれも繰り返しの部分が入っています。
「大きなかぶ」ではかぶを引き抜く際に決まった言葉があります。
「うんとこしょ どっこいしょ それでもかぶは ぬけません。」
大人にとっては繰り返して何が面白いの?となりそうですが、子どもは違います。
ママやパパなら、お子さんから「これ読んで〜!」と同じ絵本ばかり読まされる…なんて経験あるのではないでしょうか?
子どもは知っているものと出会うのが大好きなんです。
繰り返しがあると安心して見ることができるのです。
実際に保育園で働いていた際に「大きなかぶ」を子どもたちに読み聞かせると、みんな大きな声で繰り返しのフレーズを言いながら見てくれていました。
中には立ち上がって引っ張る動作をする子の姿も…!笑
”繰り返しを入れる”は絵本を描く上では欠かせないポイントです。
⑤実際にかく
いよいよ実際に書き出してみましょう!
紙やスマホ・ipadなど、まずは難しく考えずに描いてみましょう。
子どもは説明よりも言葉の音やリズムを楽しみます。
また、難しい言葉よりもドンドン・カンカン・えーんえーん・ツルツル・キラキラなどの擬音語・擬態語の方が伝わりやすいので入れてみて、よりわかりやすく仕上げていきましょう。
2、イラスト・製本の仕方
イラストや製本の仕方は下記の通りです。
- ①ページ数を決める
- ②イラストをつけていく
くわしく解説します。
①ページ数を決める
絵本は16ページか32ページで作られているものが多いです。
3歳以下なら16ページの短時間で読めるもの、4歳以上であれば32ページの
作品が望ましいです。
物語の作り方で決めたターゲットの年齢を元にページ数を決めましょう。
②イラストをつけていく
物語は決めたけど、絵をうまく描けない…なんて方も多いかと思います。
イラストをうまく書けるようにするには、自分が好きだな〜と思う絵本やイラストを見つけて、とにかく真似をすることです。
実際にイラストをつけ、製本をしていきます。物語は出来ても、「イラストがどうしても書けない!」「製本の仕方がわからない」方も多くいるかと思います。
自分(もしくは自身の子ども)が好きな絵柄やプロの絵本を見て、沢山真似たり研究をすることで素敵な作品を生み出す一歩となります。
3、出版・製本の種類
出版・製本の種類は下記の3点です。
- ①出版社に郵送・もしくは持ち込み
- ②コンクールや賞に応募する
- ③オリジナルの絵本を作る
是非参考にしてくださいね!
①出版社に郵送・もしくは持ち込み
出版社に自分の作品を売り込みに行くというのは昔からあるよく知られた出版の方法で、作品が評価されたら出版することが可能です。
しかし、出版社への持ち込み・郵送をして出版するというのはとてもハードルが高いのも事実です。
②コンクールや賞に応募する
文芸社や絵本出版.comなど、様々なコンクールや賞に応募する方法があります。
コンクールや賞は、誰でも簡単に応募することができます。ストーリーのみの部門があるコンクールも多いので、イラストに自信がない方でも挑戦しやすいですね!
そして何よりも出版社に郵送・持ち込みするよりもひとつひとつの作品を丁寧に見てもらいやすいのが特徴です。大きなコンクールですと賞を取れなくても、望めばアドバイスが受けられたりもするので、ある程度形が出来たら応募してみるのもひとつの手段です。
③オリジナルの絵本を作る
持ち込みや賞以外には、オリジナルの絵本を作るという方法があります。
手作りで作る方法と、自費出版の方法があります。
”出版”ではなく絵本を形にして残したい・誰かにプレゼントしたいという方にはオリジナル絵本を作る方法がおすすめです。
最後に絵本を作る方に個人的におすすめの本をご紹介致します。
![]()
 |
絵本作家になりたくて ぐーたらブー子の奮闘記 [ 有田奈央 ] 価格:1320円 |
こちらは漫画で書かれていて、本が苦手な方でもスラスラと読める本です! 著者が絵本作家になるまでの道のりなどが描かれています。
・これを読めば「絵本作家」になれる絵本の作り方の教科書 著:ユウトモ
こちらは物語を作るにあたり、大事になる起承転結についてわかりやすく書かれています。こちらもほとんどのページにイラストが入っており、読みやすい作品となっております。
![]()
4、年齢別!おすすめ絵本 〜乳児・幼児別おすすめ絵本紹介〜
この章では、元保育士の私がおすすめしたい年齢別の絵本を紹介します。保育園や幼稚園で人気の絵本ばかりですので、知っているものもあるかもしれません。
0・1・2歳児向け 赤ちゃんクラス
「きんぎょがにげた」
きんぎょがにげた、どこににげた?と子どもたちに問いながら金魚を探していく絵本。ページをめくるたびに逃げた金魚がどこかに隠れています。
「だるまさん」シリーズ
大人気のだるまさんシリーズ!「だ・る・ま・さ・ん・が〜」の後にだるまさんが「びろーん」と伸びたり、しぼんだり、「め」と目が大きくなったりする絵本。小さい子でも言葉や動きを真似しやすく、人気の商品です。
3・4歳児 年少クラス
「まるまるまるのほん」
”絵本”を実際にゆすってページをめくると”まる”が増えたり、傾いたりする遊びながら楽しめる絵本。
子どもが自分で見ても楽しい作品です。
4・5歳児 年中クラス
「どうぞのいす」
うさぎさんが作った椅子をめぐって次々に繰り広げられるとりかえっこ。「どうぞ」にこめられたやさしさが伝わってくるロングセラー絵本。
「どうぞならばえんりょなくいただきましょう」と繰り返しが使われている絵本です。
「めっきらもっきらどおんどおん」
何ともへんてこな世界で住人“もんもんびゃっこ”“しっかかもっかか”“おたからまんちん”とかんたは仲良しになり、時のたつのを忘れて遊び回るお話。
「めっきらもっきらどおんどおん」の繰り返される”ヘンテコな歌”が頭から離れなくなり、子どもたちも一緒に歌いながら楽しむ人気の作品です。
「ほげちゃん」
ぬいぐるみのほげちゃんは、小さなゆうちゃんといつも一緒なので汚れ放題。そのせいでおでかけの日にも置いてけぼりになり、もうカンカン!
一度読んだら忘れられない、大人も子どももつい笑ってしまう作品です。
5・6歳児 年長クラス
「りんごかもしれない」
ある日、男の子が学校から帰ってくると、テーブルのうえにリンゴが置いてありました。しかし、そのりんごを見て、とある疑問を抱いてしまった男の子。
「もしかしたらこれは、りんごじゃないのかもしれない」
りんごがりんごであることを疑う男の子の想像は、とどまるところを知らずにどんどん大きくなっていきます。
子どもの想像力を広げながら楽しめる作品です。
「スイミー」
ある日、恐ろしいマグロがやってきて、小さな魚の兄弟を残らず飲み込んでしまいます。 逃げ延びたのは、スイミーだけ。 たった一匹になってしまったスイミーは、寂しさや悲しさと戦いながら、暗く広い海を冒険します。 そして、すばらしい物と出会い、だんだんと元気を取り戻していくのです。
今回は絵本の物語を作るところから製作・出版までをまとめてみました。
- 物語はテーマ・ターゲット・キャラクターを考えてから構成する。
- 自分の好きな絵本や絵柄を見つけて真似たり、研究したりする。
- 自分に合った製本・出版方法を見つける。
実際に絵本の作り方で悩まれる方も多くいるかと思います。是非上記を参考にしていただいて、素敵な絵本を作ってくださいね!
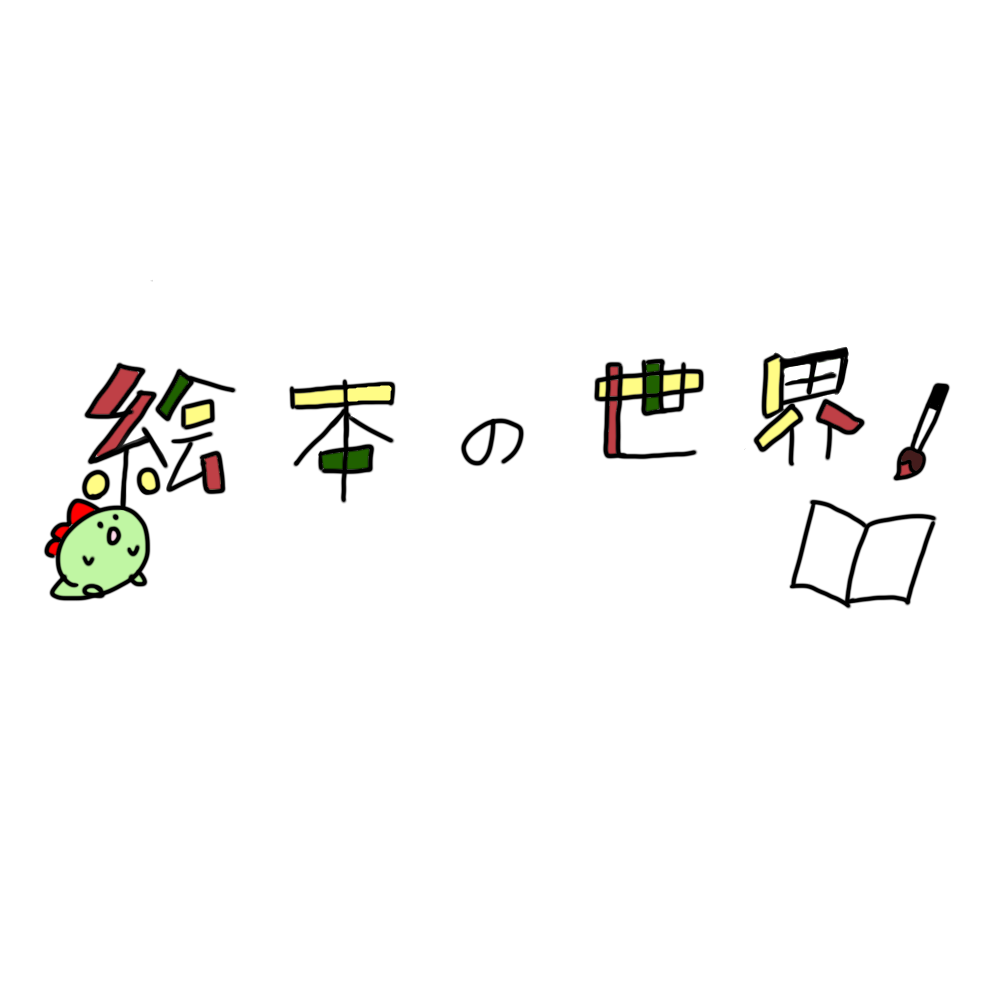

コメント